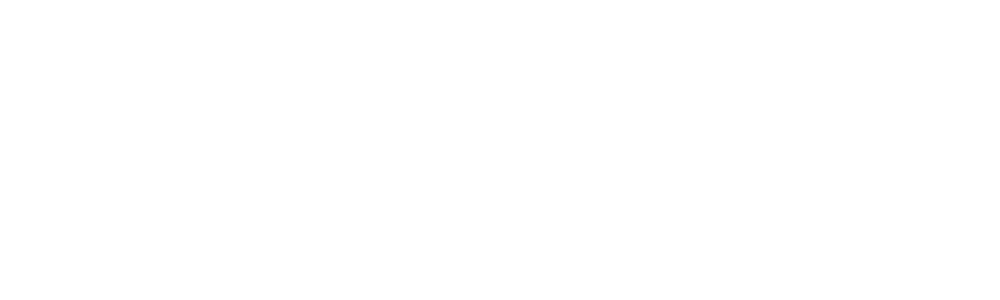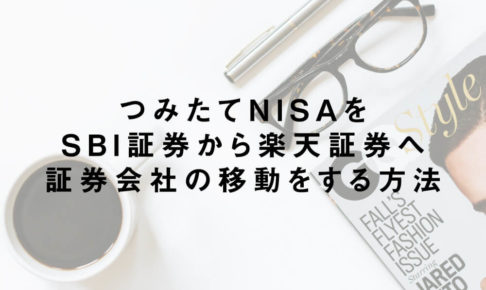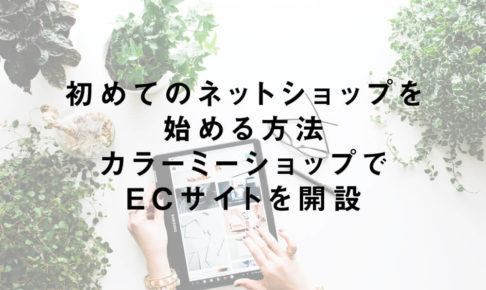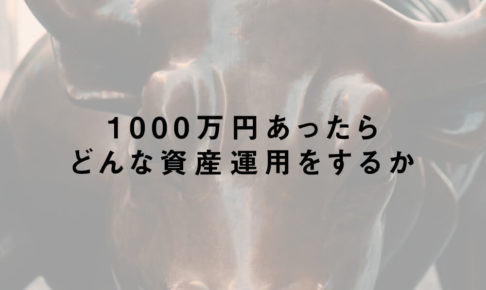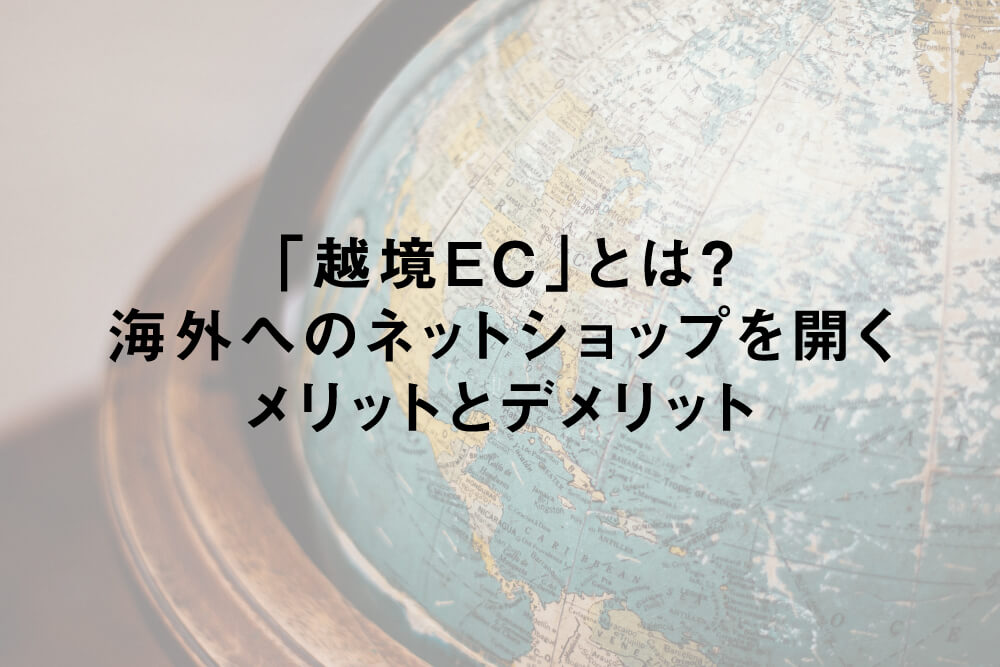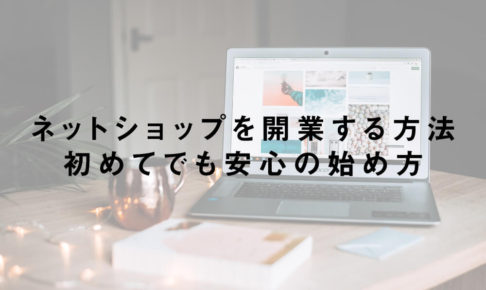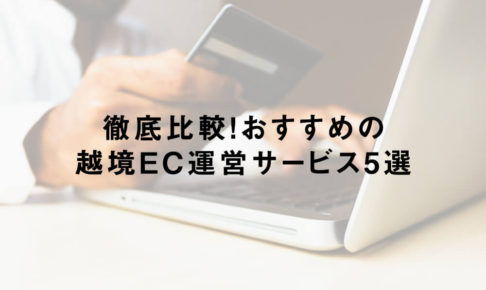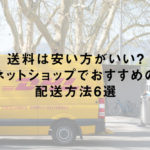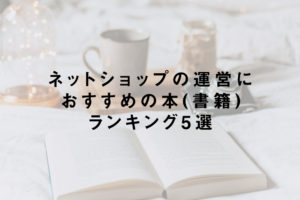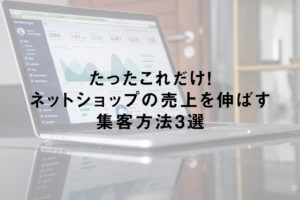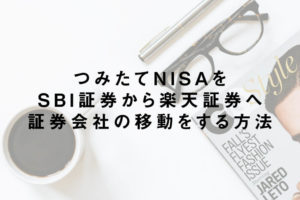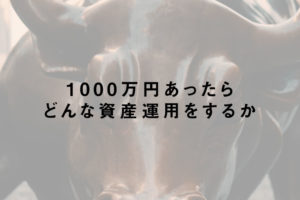こんにちは。ネットショップコンサルタントの「たぶ」(@yusuke_tanaka34)です。
今日は『「越境EC」とは?海外へのネットショップを開くメリットとデメリット』をご紹介していこうと思います!
今回の記事は、
- 海外に商品を販売したい方
- 「越境EC」に興味がある方
- ネットショップの売り上げを伸ばしたい方
におすすめです!
ネットショップの担当者さんや取引先から、最近こんな質問をいただきます。


そうですよね。数年前から「越境EC」という言葉を耳にするようになりました。
「越境EC」って、全然聞きなれない言葉ですよね。僕も最初に「越境EC」という言葉を聞いた時は「なにそれ?」って感じでした。
でも、それから数年経って、だいぶ「越境EC」というキーワードが一般的になってきました。
今回は、改めて「越境ECとは何か」について解説していきたいと思います。
「越境EC」を始めるには、まず「越境EC」とは何なのか、「越境EC」のメリット・デメリットなんかを知らないといけないですよね。
この記事に書いてある『「越境EC」とは?海外へのネットショップを開くメリットとデメリット』を読めば、「越境EC」の基礎からメリット・デメリットまでが分かっちゃいます!
「越境EC」とは「日本国内だけでなく海外にもネットショップで商品を販売すること」。
今回は、その中でも、
- 「越境EC」の市場規模
- 「越境EC」のメリット・デメリット
に焦点を当てて解説していきたいと思います。
「越境EC」の現状を把握したら、次は「越境EC運営サービス」を選んでいきましょう!
おすすめの「越境EC運営サービス」は「Shopify」です。
それでは、実際に『「越境EC」とは?海外へのネットショップを開くメリットとデメリット』をご紹介していきますね。
スポンサーリンク
「越境EC」とは

「越境EC」とは「日本国内だけでなく海外にもネットショップで商品を販売すること」のことを言います。
「国の境を越えた電子商取引(Electronic Commerce)」の略ですね。
日本国内向けのネットショップである程度の実績ができてくると、販路拡大のために「海外に進出しよう!」となるのは自然な流れです。
インターネットの普及により、僕たちは海外とも気軽につながることができるようになりました。
海外の企業である「Google」や「Amazon」、「Facebook」や「Apple」はすべてアメリカの企業。日本でも当たり前のように浸透していますよね。(世に言う「GAFA」ってやつです。)
物流さえ整っていれば、世界中のどこの商品でも購入できるようになりました。
日本の製品は、
- 海外でも「高品質で安心・安全」と認識されていること
- 海外では日本の製品があまり普及していないこと
- 日本の会社で積極的に「越境EC」に乗り出している企業が少ないこと
から、日本製品の「越境EC」は今後より注目される市場になっていくと予想されます。
ここ数年はインバウンド市場も拡大しており、中国や欧米からの観光客が日本の製品に触れることで、日本製品に対する購買意欲は高まっています。
帰国後もリピート購入をしたり、友人などへの口コミなどもあって、日本製品の「越境EC」が求められいるのです。
実際、「Google Analytics」などを見ていただくと分かるのですが、実はすでに「2%~8%」ほど海外からの検索もされているのです。
現在、日本語で日本人向けに商品を販売しているため、この「2%~8%」はまだ売上にはつながっていませんが、それだけ海外の方から興味を持ってもらっているというだけで、ワクワクしますよね!
海外に向けて「越境EC」をオープンすれば、EC事業の売上拡大につなげることは間違いなしです。
今後、「越境EC」を始めるにあたって、
- 言語の問題(顧客対応)
- 為替の問題(決済)
- 関税の問題(配送)
- コストの問題(人材)
の4つがハードルになってきます。
ネットショップ担当者にとって、「越境EC」はハードル(困難)も多いですが、「ネットショップの売上を上げる」という目標を考えると、かなり有効な一手だと思います。
2019年10月に行われる消費税増税や、2020年のオリンピック後の景気後退を考えると、今後は消費が落ち込むことが予想されます。
また、日本の少子高齢化問題も考えると、国内のネットショップも今後苦境に立たされる可能性があります。
しかし、海外に目を向けると、中国や東南アジアは景気の拡大で消費は伸び、欧米ではすでに大きな市場があるため、販路の拡大を目標に海外に進出していくことは、大きな可能性を秘めています。
特に日本のkawaii文化やコスプレ、漫画やアニメなどは海外にも広く受け入れられています。
また、観光として日本を訪れた外国人が「帰国してからネットショップを探したけど、日本の製品がない!」というニーズにも応えることができます。
「世界の人々に良質な日本の製品を届ける」という意味でも、「越境EC」をやる意味は大きいと思います。
売上増加に対する「越境EC」の有効性を見てきましたが、実際「越境EC」の市場規模はどれくらいなのでしょうか?
次に「越境EC」の市場規模について見ていきたいと思います。
「越境EC」の市場規模

まず、「越境EC」の市場規模ですが、世界のEC市場規模は「313兆円」です。
このうち、アジア太平洋地域は「190兆円」で全世界の「61%」を占めています。
特に中国の割合が大きく、EC市場の「52%」。アメリカは「18%」。日本は「4%」という結果になりました。
世界のEC市場市場規模は313兆円(図表18、左図)。このうち、アジア太平洋地域は190兆円で、61%であった。(図表19左図)
中国は小売市場に占める割合は22%と米国と同程度であるものの、EC市場に占める割合は52%で、米国の3倍近くの規模であった。
世界の小売市場に占めるEC市場規模の割合は約12%であった。
ちなみに、日本のEC業界の市場規模は2018年で「17兆9,845億円」でした。
2010年の市場規模が「7兆7,880億円」だったので、8年間で「約10兆円」増加したことになります。
【日本のEC業界の市場規模】
| 2010年 | 7兆7,880億円 |
|---|---|
| 2011年 | 8兆4,590億円 |
| 2012年 | 9兆5,130億円 |
| 2013年 | 11兆1,660億円 |
| 2014年 | 12兆7,970億円 |
| 2015年 | 13兆7,746億円 |
| 2016年 | 15兆1,358億円 |
| 2017年 | 16兆5,054億円 |
| 2018年 | 17兆9,845億円 |
「約313兆円」の中の「約18兆円」しか日本の製品は占めていないんですね。
まだまだ市場規模を増やせそうで、ワクワクしてきますね!
ちなみに、日本のEC市場はアメリカ・中国に次いで世界で3番目。
世界的に見ると、大きな市場なんですね。
主要な国である、アメリカ・中国との「越境EC」の市場規模を見てみると、
各国間の越境EC市場規模の推計結果は、次に示す図表の通りとなった(図表1-8)。
日本の越境BtoC-EC(米国・中国)の総市場規模は2,765億円となった。このうち、米国経由の市場規模は2,504億円、中国経由の市場規模は261億円であった。
米国の越境BtoC-EC(日本・中国)の総市場規模は13,921億円となった。このうち、日本経由の市場規模は8,238億円、中国経由の市場規模は5,683億円であった。
中国の越境BtoC-EC(日本・米国)の総市場規模32,623億円となった。このうち、日本経由の市場規模は15,345億円、米国経由の市場規模は17,278億円であった。
【各国間の越境EC市場規模】
日本 米国 中国 合計 日本 – 2,504億円 261億円 2,765億円 米国 8,238億円 – 5,683億円 1兆3,921億円 中国 1兆5,345億円 1兆7,278億円 – 3兆2,623億円
アメリカや中国と比べると、日本はまだまだ「越境EC」の利用額が少ないですね。
逆に、アメリカや中国は日本から、結構な金額「越境EC」を利用して購入しているんですね。
現状、日本からアメリカや中国に輸出している金額は「2兆3,583億円」。
日本国内の「17兆9,845億円」と比べても、「約13%」しか海外へ販売していません。
ただ、「爆買い」ですごく購入されているイメージのある「インバウンド」ですが、中国やアメリカが日本を訪れて商品を購入していく金額は「1兆8,343億円」なんです。(2018年)
「越境EC」での購入金額と比較すると、意外にも「越境EC」の方が「5,000億円」以上、上回っています。
【訪日外国人消費動向調査|国土交通省観光庁】
http://www.mlit.go.jp/common/001283138.pdf
「爆買い」よりも「越境EC」の方が、市場規模が大きいんですね。
また、日本・アメリカ・中国の「越境EC」の今後の市場規模ですが、経済産業省のデータによると2022年にはアメリカへ「1兆3,925億円」、中国へは「2兆5,144億円」、合計「3兆9,069億円」程度になると予想されています。
2018年と比べると「約165%」となります。
【各国越境E市場規模推計(2018年〜2022年)】単位:億円
消費国 販売国 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 日本 米国 2,504 2,604 2,698 2,782 2,857 中国 261 271 281 290 298 米国 日本 8,238 9,457 10,810 12,291 13,925 中国 5,683 6,524 7,457 8,479 9,606 中国 日本 15,345 18,184 20,730 23,217 25,144 米国 17,278 20,474 23,341 26,142 28,312
中国は、2017年時点で人口が「13億8,823万人」。その中でインターネット人口が「7億5,381万人」。インターネット普及率は「54.3%」に止まっています。
インターネット普及率が50%台でこの金額ですから、インターネット普及率が増えればまだまだ伸びしろは大きいです。
インターネット普及率の比較的高い日本・アメリカ・中国の3ヶ国だけを見てこの数字なので、まだインターネット普及率の高くない途上国も含めると、「越境EC」の市場規模はまだまだ可能性があります。
また、経済産業省も「2021年まで前年比2ケタ成長する」と言っていますし、今後はテクノロジーの発達により、どんどん国や地域の境は薄くなっていくので、「越境EC」はより伸びていく市場だと思います。
スポンサーリンク
「越境EC」が今後も伸びる理由

「越境EC」は今後も伸びていくことが予想されます。
「越境EC」が今後も伸びていくことが予想される理由としては、
- IoTの普及
- 「Amazon」や「Alibaba」の躍進
- 市場規模が拡大していること
などが挙げられます。
僕自身、取引先から「越境EC」のことはよく聞かれますし、取引先もおそらく1年以内には「越境EC」に進出すると思います。
Google検索でも「越境EC」というキーワードは、ここ1年で月間「5,000〜7,000回」検索されています。
「越境EC」が一番盛り上がっていたのは2016年で、4月には「12,100回」、11月には「14,800回」と、かなり注目されていました。
【「越境EC」の月間検索数】
| 2015年8月 | 2,900 |
|---|---|
| 2016年4月 | 12,100 |
| 2016年7月 | 9,900 |
| 2016年11月 | 14,800 |
| 2017年7月 | 8,100 |
| 2018年7月 | 6,600 |
| 2019年7月 | 6,600 |
「越境EC」と検索するのはネットショップ関係の人だと思うので、ネットショップ業界の人達はかなり「越境EC」に興味があると言えます。
これだけ注目度が高ければ、一定の確率で「越境EC」に参入してくると思われるので、経済産業省も言っていたとおり「2021年まで前年比2ケタ成長する」でしょう。
むしろ、2020年のオリンピック需要が終わった後は、インバウンドが落ち着くと思うので、「越境EC」がもっと伸びるかもしれませんね。
それでは、「越境EC」が今後も伸びる理由について、見ていきたいと思います。
「越境EC」が伸びる理由1:IoTの普及
「IoT」とは、「Internet of Things」の略です。
要するに「あらゆるものがインターネットに接続され、それを利用することができる。」という便利な世の中です。
2019年現在、世界中にスマートフォンが普及したことで、ネットショップでの買い物が大幅に増えました。
スマートフォン1台で、ネットショップやショッピングモールにアクセスし、Amazonや楽天、ZOZOなどで買い物を楽しんでいます。
特に物販系の分野がスマートフォン経由で売れているらしく、「6,462億円」増の前年比「+21.5%」だったそうです。
【平成30年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)|経済産業省】
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf
僕もネットショップを運営していて、2014年の6月頃からパソコンからの売上をスマートフォンの売上が越えました。
最近では、「スマートフォン7割・パソコン3割」といったところです。
それくらい、スマートフォンが生活に浸透したということですね。
今はまだ、いくつかの問題点がありますが、今後はテクノロジーの発達により、より手軽に「越境EC」で買い物ができるようになっていきます。
最初に出てきた「言語」「決済」「配送」などの問題は、テクノロジーの発達により、解消が可能です。
今後は、スマートフォン以上に便利な機器が出てくることでしょう。
(僕は個人的に「Google Glass」的なものだと思っているのですが、それ以外かもしれません。)
そういった、新しい端末の出現によって、今以上にネットショッピングが身近になり、ネットショップで商品を購入する人が、今以上に増えていきます。
また、今後は「4G」から「5G」への切り替えが行われるので、今までの何倍も速い通信速度でページを見ることができます。
より高画質な商品画像や動画、VR・ARのような容量の大きなデータも素早く転送することができます。
ストレスのない通信を行うことができるようになることで、より快適なネットショッピングを楽しむことができます。
IoTの普及やインターネット環境の発達により、「越境EC」の市場規模はより伸びていくでしょう。
「越境EC」が伸びる理由2:「Amazon」や「Alibaba」の躍進
日本でも「楽天」や「ZOZO」などが上場している大きな企業ですが、世界でも「Amazon」や「Alibaba」など、EC関連の会社が大躍進しています。
日本でもなじみの深い「Amazon」は世界の時価総額ランキングで第3位。時価総額は8749億ドルに上ります。(2019年8月現在)
「Amazon」は18ヵ国にマーケットプレイスを持っていて、配送可能な国は146ヵ国。
また、あまり日本での浸透率は高くありませんが「Alibaba」は世界の時価総額ランキングで第8位。時価総額は4319億ドル。(2019年8月現在)
こちらもかなりの大企業です。「Alibaba」では190ヵ国に販売することが可能です。
こういった「Amazon」や「Alibaba」などのショッピングモールの躍進により、世界中のどこにいても気軽に商品を購入することができるようになりました。
現在、「Amazon」や「Alibaba」などの大企業がどんどん新しい技術に投資をし、テクノロジーの開発を進めています。
まだ「越境EC」のすべてのハードル(困難)は解決していませんが、今後テクノロジーの進歩により、より簡単に「越境EC」が始められるようになると思います。
また、お客さん側も「Amazon」や「Alibaba」のような大企業が一般化してくることで、「越境EC」に対する抵抗は減り、「越境EC」で買い物をすることが当たり前になってくるでしょう。
今後も「Amazon」や「Alibaba」がEC業界の覇権を握り続けるかは分かりませんが、今後もEC関連企業がEC業界を盛り上げてくれることは間違いありません。
「越境EC」が伸びる理由3:市場規模が拡大していること
上記の「越境ECの市場規模」でもあった通り、「越境EC」の市場規模は右肩上がりで伸びています。
現在、日本から「越境EC」を通して輸出している金額は、中国とアメリカのみで「2兆3,583億円」。
世界では「約313兆円」の取引が行われ、日本国内でも「約18兆円」がオンライン上で取引されています。
比較すると「越境EC」がまだまだ始まったばかり。
経済産業省も「2021年まで前年比2ケタ成長する」と言っているとおり、今後数年も右肩上がりで成長することは間違いありません。
「越境EC」に取り組むことで、「約313兆円」の市場に打って出るわけですから、夢は広がるばかりです。
また、上記の「2兆3,583億円」は中国とアメリカのみなので、これから伸びてくる新興国などを考えると、「越境EC」の伸び率は未知数です。
アメリカの「Amazon.com」で検索しても、日本のアニメ関連商品や陶器製品、箸などの日本独自の製品は人気です。
2020年のオリンピックに向けて、日本を訪れる外国人は増え、日本への注目度も高まります。
その上で、日本に滞在した外国人が日本の製品を購入し、自国に帰った後、「越境EC」を利用して日本の製品を購入するという流れが起こります。
また、パソコン上で日本のコンテンツ(アニメや映画)に触れ、日本に興味を持つ外国人も少なくありません。
僕の友人の旦那さんも、日本のアニメや文化がもともと好きで、僕の友人と結婚しました。(ちなみにフランスの方です。)
そういった場合も「越境EC」なら、日本に足を運んだことがなくても、興味を持ったコンテンツや関連商品を気軽に購入することができます。
日本には、海外の人がまだ知らないような日本独自の文化やコンテンツが多く存在しています。
そういった「潜在ニーズ」を喚起することができれば、「越境EC」は今後も伸びていく可能性を秘めています。
それでは、次に「越境EC」のメリット・デメリットを見ていきたいと思います。
「越境EC」のメリットとデメリット

「越境EC」のメリット・デメリットですが、
【「越境EC」のメリット・デメリット】
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
などが、考えられます。
それでは、「越境EC」のメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
「越境EC」のメリット1:販路・売上の拡大
「越境EC」を始めることによって、販路・売上を拡大することができます。
日本国内のEC市場規模は「約18兆円」。それに対し、世界のEC市場規模は「約313兆円」。
単純に計算しても「17.3倍」の市場規模があるので、「越境EC」により世界へ向けたネットショップを開くだけで、売上が伸びる可能性が高くなります。
また、現在海外への卸売り等を行っていない場合、直接お客さんへ発送することで、大幅に販路を拡大することができます。
海外へ卸売りを行っている取引先の担当者は、

と言っていました。
その点、「越境EC」であれば、配送料は日本国内に比べると高くなってしまいますが、卸売りで手数料がかかる場合に比べると、安価に商品を配送することができます。
世界の人口は「約77億人」。その中でも、日本の人口は「約1億2,623万人」の小さな島国です。
今後は少子高齢化の影響により、日本の人口も減少していくと考えられています。
それならば、今から「越境EC」を始めて、全世界への販路を育てていきたいですよね。
「約77億人に向けて商品を販売できる。」と考えただけでも、ワクワクしてきますよね!
「越境EC」のメリット2:店舗を構えるリスクの回避
「越境EC」なら、海外に店舗を構える必要がありません。
世界には日本以外に195ヵ国の国があります。(この195ヵ国は日本が承認した国の数です。厳密にはもっと多くの国があると思われます。)
言語の問題さえクリアできれば、オンライン上の1つの店舗で、この195ヵ国に自社の商品を販売することができるのです。
195ヵ国すべてに店舗を構えようとすると、時間もお金も膨大なものになってしまいます。
家賃・内装費・商品の調達費・人件費・各種申請など、店舗をオープンするだけで、数ヶ月の期間と数百万~数千万の費用が掛かります。
「越境EC」なら、各国に店舗を構えることに比べて、圧倒的に小さなリスクで始めることができます。
どこのシステムを使うかによりますが、数万円~数十万円もあれば「越境EC」を始めることができます。
日本にいながら低リスクで海外の市場へ進出できるというのは、大きなメリットですよね。
「越境EC」のメリット3:日本の製品を海外へ届けることができる
「越境EC」を始めることで、日本の製品を海外へ届けることができます。
上記の通り、2018年の中国とアメリカのインバウンド市場規模は「1兆8,343億円」。
「越境EC」では、すでに「2兆3,583億円」の市場規模があります。
他の国も合わせると、より大きな市場が「越境EC」には存在しています。
「インバウンド」や「越境EC」は、右肩上がりで成長を続け、経済産業省も「2021年まで前年比2ケタ成長する」と言っています。
旅行で日本を訪れ、自国で日本の商品を探したり、何度も日本を訪れたりする人も多いようです。
それだけ、日本の文化や商品には注目が集まっており、世界中で日本の商品を求めている人がいるということです。
そのように、日本に興味を持ってくれ、日本の製品を求めてくれる人に、商品を届けるということだけでも、「越境EC」をやる意味がありますよね。
もし海外のお客さんに適切に商品を届けることができれば、口コミなどで自社の商品を知ってもらう機会が増えます。
最初は小さな1歩かもしれませんが、そうやってコツコツ続けていくことで、ゆくゆくは大きく市場を広げていくことができるのです。
「求めてくれる人に、しっかりと商品を届ける。」これだけでも「越境EC」やるメリットがあると思います。
以上、3点が「越境EC」のメリットでした。
「越境EC」のデメリット1:顧客対応が大変
「越境EC」をやる上で、言語の問題は大きいです。
どこの国に販売するかによりますが、お問い合わせとクレームに対応できる程度の「英語力」は必要になってきます。
また、英語で記入する書類などもある可能性があります。
「商品説明文」も英語で記入することができれば、多くの人に商品をアプローチすることができますね。
今は「Google翻訳」などがあるので、昔よりはハードルは下がりましたが、やはり「日本語しかできない。」という状態だと、少し不安な面があることは拭えません。
ただ、ビジネス英会話ができるレベルは必要ないです。
「英語で送られてきたメールを、調べながら適切に返答できる。」という、文章を書く英語力で大丈夫です。
この点は、翻訳サービスを利用したり、英語に強い人材を雇用したり、英語が得意な知人・友人に聞いたりすることで、解消することができます。
実際に「越境EC」を始めて対応していけば、どんどんスキルは上達していくので、まずは「越境EC」を始めてみましょう。
「越境EC」のデメリット2:決済が複雑
「越境EC」を始めるにあたり、「決済」の問題が出てきます。
どの決済サービスを利用するかによるのですが、海外のお客さんは基本的に自国の通貨で決済を行います。
まずは、日本の決済代行サービスの中で「外貨建て決済」に対応している決済代行サービスを探す必要があります。
また、商品詳細ページに、各国の通貨に対応した表示を行わなければいけません。
システム上・サービス上で、まずは解決すべき問題が発生します。
次に「為替」の問題も発生してきます。
たとえば、基本的にアメリカであれば「ドル」で入金があるわけです。
商品を販売した時は「1ドル=100円」だったのに、日本円に引き換える時に「1ドル=80円」になっていた場合、単純に売上金額が「20%」減ったことと同じ現象が起きます。
商品を輸出するには逃れられないリスクではありますが、この「為替リスク」を知っておくことは重要です。
ちなみに、この「決済」の問題は「越境EC運営サービス」や「決済サービス」である程度解消することができます。
「越境EC」のデメリット3:配送が手間
「越境EC」の場合、日本国内に比べて「配送」の手間が発生してきます。
たとえば、郵便局から商品を発送する場合、「インボイス」や「税関告知書」が必要です。
【インボイスについて】
https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/invoice.html
【税関告知書について】
https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/customs.html
ものすごく複雑な書類ではないですが、やはり国内の配送に比べると、手間がかかってしまうのはしょうがないですよね。
また、配送料や手数料も国内の配送に比べると高くなってしまいます。
手紙くらいの大きさだとけっこう安く送ることができますが、大きめの商品だとかなり高額になってしまいます。
また、少量であれば大丈夫ですが、大きめの荷物になってくると、「関税」が発生します。
法律も国によって違ってきますので、「越境EC」で取り扱う商品の輸出入が禁止されていないかどうか、販売する国の法律を事前にチェックしておきましょう。
関税や輸出入禁止商品などは「ジェトロ(JETRO)」などで調べることができるので、分からない場合は相談してみるといいかもしれません。
「配送の問題」は、慣れてくればある程度解消されると思います。また、配送料金が高いのはお客さんも分かっていることなので、そこまで大きな問題ではありません。
「越境EC」のデメリット4:代金や商品が届かない可能性
「越境EC」と言いますか、海外では商品代金がもらえなかったり、商品が届かなかったりという可能性が、日本よりは高いです。
これはどこの国に向けて発送するかによりますが、「日本以上にスムーズに取引ができる国はない。」と思っていていいかもしれません。
日本はストライキやデモなどがあまり起こりませんが、海外ではストライキやデモなどは頻繁に起こっていますし、紛争や内戦などが起こっている国さえあります。
また、ニュースなどでたまに目にすることがありますが、ハリケーンや大雪、地震などの天災も起こる可能性があります。
日本ではあまり起こらないようなことが、海外では発生するのです。
また、商品の紛失や盗難も起こる可能性があります。
海外の配送会社は日本とは違い、丁寧に商品を扱ってくれません。(もちろん国によります。)
映画などを見ていてもたまにそういうシーンが出てきますが、普通に荷物をぶん投げたりします。(笑)
そのため、日本を出る時は綺麗に梱包された商品でも、お客さんに届く頃にはボロボロになっているなんていう可能性もあるのです。
商品の金額にもよりますが、なるべく保険はかけておいた方が安心です。
日本の配送がどれだけ安心できて優れているかが分かると思います。日本の配送業者さんには感謝しかないです。
この事実は、知っておくのと知らないのでは全然違うので、「こういう可能性があるんだ。」というのは、知っておくといいかもしれません。
以上、4点が「越境EC」のデメリットでした。
スポンサーリンク
まとめ
今回は『「越境EC」とは?海外へのネットショップを開くメリットとデメリット』というテーマでお送りしてきました。
「越境EC」とは
「日本国内だけでなく海外にもネットショップで商品を販売すること」
でした。
2018年の「越境EC」の市場規模は、
「約313兆円」
その中で、日本が「越境EC」を通して、中国とアメリカに販売している金額は、
「2兆3,583億円」
でした。
「越境EC」は今後も伸びていくことが予想されます。
「越境EC」が今後も伸びる理由は、
- IoTの普及
- 「Amazon」や「Alibaba」の躍進
- 市場規模が拡大していること
などが挙げられます。
「越境EC」のメリット・デメリットは、
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
でした。
日本の少子高齢化や不景気の懸念を考えると、ちょうど今「越境EC」を始めて、「約313兆」の市場規模がある世界に進出しておくことは、有効な一手だと思います。
この記事を見ているということは、今が「越境EC」を始めるチャンスかもしれません!
「越境EC」を始めるなら「Shopify」がおすすめです。
ネットショップや「越境EC」ついて、他にも分からないことがありましたら、お問い合わせまでご連絡ください。
以上、ネットショップコンサルタントの「たぶ」でした。
こちらの記事もおすすめです。